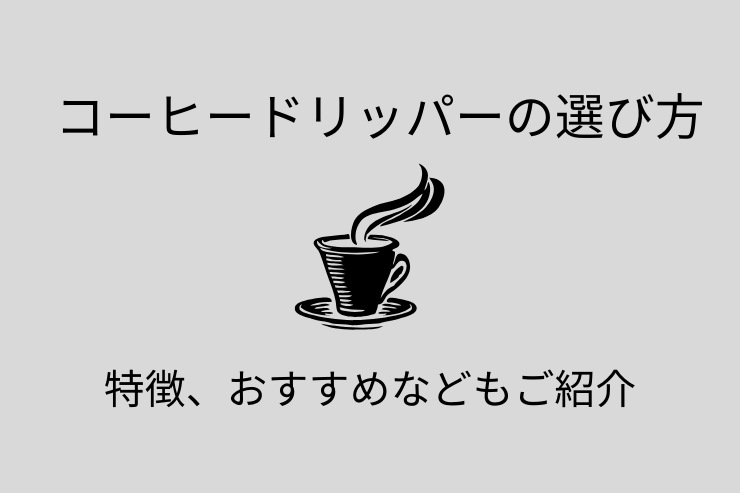今日も、ten to ten(テントゥテン)にご訪問頂き、ありがとうございます。
ten to ten(テントゥテン)では、「自分好みのコーヒーに出合う」をテーマに、コーヒーに関する情報をお届けしています。
今回ご紹介する内容は、「コーヒードリッパーの選び方」です。
自宅でコーヒーを飲みたいな〜という時、人気の抽出方法の一つに、ペーパードリップがあります。
ペーパードリップに必要な器具はさまざまですが、欠かせないアイテムの1つにコーヒードリッパーがあります。
このコーヒードリッパーは、比較的安価で販売されているので、手軽に購入することが出来ます。
コーヒーに興味があるみなさんの中には、すでに色々と調べている人もいると思います♪
ですが、「コーヒードリッパー」を調べてみると、実にたくさん種類が存在しているということに、驚かれたのではないでしょうか!?
メーカーがたくさん、その形も同じような感じで色々.....
ペーパードリップの必需なのに、「どんな選び方をすればいいのかわからない」、とお悩みの人も多いはずです。
また、「コーヒードリッパーはどれでも同じじゃないの?」「ドリッパーでコーヒーの味って変わるって本当?」と疑問を持たれている人もいるでしょうね。
実は、コーヒードリッパーの形状は、仕上がりの味に大きな影響を与えているんですよ!
コーヒーの好みは十人十色で、すっきりしたコーヒーが好き、しっかりとした苦みがあるコーヒーが好き、など人それぞれです。
自分が飲みたい味を出せるドリッパーの選び方は、それぞれの形状の違いを知ることから始まります。
今回の記事では、自分の好みの味を出せるドリッパーが見つけやすくなるような、選び方のポイントをご紹介していきます!
おおまかなドリッパーの種類や特徴はもちろん、有名メーカーやおすすめのおしゃれなドリッパーまで、幅広く解説しています。
形状の種類や特徴、メーカーの比較まで出来るので、自分にぴったりの1品が見つかるはずですよ。
コーヒードリッパーの選び方を知って、コーヒーライフをより楽しんでくださいね♪
Contents
- 1 「コーヒードリッパー」とは、フィルターを固定するための器具
- 2 コーヒードリッパーの種類や違い・3つの選ぶポイント
- 3 代表的なメーカーのドリッパー「メリタ式」「カリタ式」「ハリオ式」「コーノ式」の4つ 違いを知って、好みのコーヒーを淹れよう
- 4 【おすすめ4選】人気コーヒードリッパーを、定番メーカーごとにご紹介
- 5 コーヒードリッパーを選ぶ時のコツ 使い方やタイプに注目すれば、自分に合ったものが選びやすい
- 6 「初心者向け」と言われるドリッパーは存在する?
- 7 いろいろあるおしゃれなドリッパーは、コーヒータイムをより楽しいものにしてくれる
- 8 最後に...|コーヒードリッパーごとに味わいが変化する! お気に入りをみつけて、さらにハンドドリップを楽しもう
「コーヒードリッパー」とは、フィルターを固定するための器具
コーヒーを楽しむための抽出方法、また、その際に必要な器具は様々です。
「コーヒードリッパー」とは、ハンドドリップに欠かせない必須アイテム!
コーヒー粉が入ったフィルターを固定し、抽出が終わるまでフィルターを支える、という役割があります。
その構造はとってもシンプルです。
お湯をコーヒー粉の入ったフィルターに注ぐと、ドリッパー内で抽出が始まります。
ドリッパーの底にあいている穴から、重力でサーバーやカップへ落ちる、という仕組みです。
構造はシンプルですが、ドリッパーには色々なバリエーションが存在しています。
全体の形状、底の穴の大きさ・数、内側に付いているリブと呼ばれる「溝」の形・数などです。
また、どんな素材で作られいるかでも、違いが生まれます。
これらの違いが組み合わさり、抽出するコーヒーのテイストが変化するのです。
選ぶドリッパーによって、仕上がりのコーヒーが変化するので、とっても奥深いですよね。
次から、コーヒードリッパーの大まかな種類や分類、特徴を詳しく見ていきましょう!
読み進めることで、自分の好みに合ったドリッパーが見つかりますよ♪
コーヒードリッパーの種類や違い・3つの選ぶポイント
さっそく、ドリッパーの形状の特徴、種類などの違いについて見ていきましょう!
代表的な3つのポイントに注目しながら、詳しく解説していきます。
その3つのポイントは、こちらです。
【コーヒードリッパーの種類や違い・3つの選ぶポイント】
- ドリッパーの形状(「円錐(えんすい)型」or「台形型」)
- ドリッパーのリブ(溝)(どんな形か)
- ドリッパーの穴の数(底に設けられたコーヒーが落ちる穴の数)
ドリッパーの形状は円錐(えんすい)か、それとも台形なのか。
ドリッパーの内側にあるリブ(溝)の形状はどんな形なのか。
また、穴は底にいくつあるのか。
このように販売されているコーヒードリッパーの特徴に注目すると、似ているようで違いがたくさん見えてきますよ。
この違いが、コーヒーの味に変化をもたらします。
どんな形状が、どんな味が出せるドリッパーかを知ると、好みにぴったりのタイプを見つけられます♪
ぜひ、読み進めながら比較してくださいね!
ドリッパーの形状|「円錐(えんすい)型」or「台形型」の2種類に大きく分けられる
3つの選ぶポイントの1つめは、ドリッパーの形状についてです。
円錐(えんすい)型と台形型の大きな違いは、コーヒーの落ち方です。
まず、円錐(えんすい)型のドリッパーからご紹介します。
1. ドリッパーの形状|「円錐(えんすい)型」
円錐(えんすい)型の特徴は、台形型と比べて底の穴が大きく、ドリッパー内で溜まらずにコーヒー液がそのまま落る、という点です。
注がれたお湯が中心に集まり、下のサーバーやカップに順番に落ちていきます。
このような落ち方だと、コーヒー豆の特徴が出やすくなり、しっかりとした味わいになります。
この円錐(えんすい)型のドリッパーは、「中級者以上向け」、と紹介されてることがあります。
穴が大きいことで、注ぐお湯の量・速さをコントロールしやすく、自分好みの味に仕上げられるからです。
また、お湯の注ぎ方で仕上がりの味が変化する、探求しがいのあるドリッパーの形状で、有名なカフェなどでもシェア率が伸びていますよ!
ハンドドリップの世界大会や、プロのバリスタの間でも、広く愛用されています。
2. ドリッパーの形状|「台形型」
台形型の特徴は、円錐(えんすい)型と比べて底の穴が小さく、ドリッパーの底でコーヒーが溜まった後に落ちることです。
円錐(えんすい)型のドリッパーと比較すると、コーヒー豆の持つ突出した特徴は出にくいですが、その分まとまった印象の味になります。
バランスが整った柔らかいコーヒーに仕上がります。
この台形型のドリッパーは、円錐(えんすい)型よりも「初心者向き」と言われます。
穴が小さいことで、コーヒー液の落ちるスピードが注ぐお湯の量・速さに左右されません。
一定の味わいに仕上げられる、というメリットは、ハンドドリップに慣れていない人や安定したコーヒーを楽しみたい人にぴったりです。
この台形型のドリッパーは、1908年 ドイツ人女性により発明されました。
「ドリッパーと言えばこの形!」と連想する人も多いのではないでしょうか?
とっても親しみを感じられます。
ドリッパーのリブ(溝)|メーカーによって違う形状をしている
「リブ」とは、ドリッパーの内側にある溝のことです。
リブの形状は、直線なのか、螺旋(らせん)状なのか、またその数や長さにより違いがあり、メーカーによってさまざまです。
リブの形状は、注がれたお湯の流れを変えます。
それにより、仕上がりのコーヒーの味に影響を与えているんですよ!
リブの数が多く、ドリッパーの上から下まで、長くしっかりとリブが刻まれていると、ペーパーフィルターとドリッパーとの間に隙間が生まれます。
この隙間がお湯の抜け道なり、注がれたお湯はスムーズに流れて抽出にかかる時間は短くなります。
このような長いリブを持つドリッパーで淹れたコーヒーは、酸味がはっきりとした印象になります。
また、リブが長いことで空気が通りやすくなり、コーヒーに含まれる炭酸ガスが抜けやすくなります。
それまで閉じ込められていたーヒー粉の美味しい成分が溶け出しやすくなる効果があるんですよ。
逆に、リブの数が少なく、ドリッパーの下部のみに刻まれているドリッパーだと、ペーパーフィルターはドリッパーにピタッと密着しやすくなります。
空気が通りにくくなり、注がれたお湯が落ちる速度は遅くなります。
リブの数が多くて長いドリッパーと比較すると、抽出にかかる時間はゆっくりになるのです。
ドリッパー内でコーヒー粉とお湯がしっかり馴染み、苦味のある深いコーヒーになります。
リブの形状でこのような違いが生まれるのは、とっても興味深いですね!
すっきり系が好きならリブの数が多くて長いドリッパーを、苦味をしっかり感じるコーヒーが好きなら、リブの数が少なく短いドリッパーを選ぶと良いでしょう。
ドリッパーの穴の数|コーヒーが落ちるスピードに変化を与える
【コーヒードリッパーの種類や違い・3つの選ぶポイント】の最後、3つ目は、ドリッパーの穴の数です。
穴の数も、実はコーヒーの味わいに変化を与えているんですよ!
多くの台形型のドリッパーは、一つ穴か、三つ穴になっています。
一つ穴の台形型のドリッパーは、ゆっくりとコーヒーが落ちるので、コーヒー粉とお湯が触れ合う時間が長くなります。
それにより、三つ穴と比較すると 重みのあるどっしりとした味わいのコーヒーに仕上がりますよ。
逆に穴の数が多い三つ穴では、一つ穴よりもコーヒーが落ちるスピードは早くなります。
同じ台形型のドリッパーでも、三つ穴の方が抽出スピードが早くなり、すっきりとした味わいになります。
(円錐型は、基本一つ穴です♪)
自分が飲みたいコーヒーはすっきり系なのか、どっしり系なのかで、いくつ穴があるドリッパーが良いのか、選びやすくなりますね!
台形型のドリッパーを使ってみたい場合は、穴の数もぜひ、注目してくださいね。
代表的なメーカーのドリッパー「メリタ式」「カリタ式」「ハリオ式」「コーノ式」の4つ
違いを知って、好みのコーヒーを淹れよう
ハンドドリップの器具を製造・販売しているメーカーは、国内、海外合わせると実にたくさんあります!
その中でも有名なのが、「Melitta(メリタ)」「Kalita(カリタ)」「Halio(ハリオ)」「KONO(コーノ)」です。
「Melitta(メリタ)」社は、ドイツ生まれの会社で、1908年に世界で初めてペーパードリップシステムを生み出しました。
当時、家庭でコーヒー淹れる場合、手間がかかる上に不衛生、粉が濾せずにカップに入ってしまうなどの問題があり、あまり美味しいものとは言えませんでした。
それを「もっと美味しくできないか?」と工夫を凝らし、開発したのが、創業者のメリタ・ベンツでした。
そのペーパードリップのシステムを、日本人の口に合うように進化させたドリッパーを販売するのは、日本の企業「Kalita(カリタ)」。
同じく日本生まれの、円錐(えんすい)型のドリッパーで有名な「HARIO(ハリオ)」。
同じく日本生まれで円錐(えんすい)型のドリッパーで知られる「KONO(コーノ)」。
これらの4社の定番メーカーが販売するコーヒードリッパーは、それぞれ特徴的な形をしているんですよ!
ハンドドリップの業界では、メーカー名にちなみ「メリタ式」「カリタ式」「ハリオ式」「コーノ式」と分類されているほどです。
それぞれに特徴のあるコーヒーが抽出できるので、メーカーの違いは、ドリッパー選びの重要なポイントになります。
以下より、それぞれのメーカーのドリッパーを、「形状」、「リブの形状」、「穴」の3つのポイントに絞って、詳しく見ていきましょう!
「メリタ式」
「メリタ式」は、台形型のドリッパーです。
リブの形状は、上から下までしっかり入っていて、穴に向かって直線になっているタイプです。
穴の数は一つで、コーヒー液が出る出口は小さいです。
穴の数は一つ、さらに大きさが小さい、ということで、コーヒーの抽出速度がブレにくくなります。
コーヒーの味わいは一定になりやすく、バランスが整った安定したコーヒーを楽しめます。
抽出時間が長くなるので、他のドリッパーと比較すると濃厚感が強めで、どっしりとしたコーヒーになるのが特徴です。
「カリタ式」
「カリタ式」は、台形型のドリッパーです。
リブの形状は、「メリタ式」と同じく上から下までしっかり入っていて、穴に向かって直線になっているタイプです。
穴の数は三つです。
コーヒー液が出る出口は小さいです。
コーヒー液が出る出口はメリタ式と同様に小さいですが、穴が一つだけのメリタ式よりも、抽出速度は速くなります。
お湯の注ぎ方を早くしたり、遅くしたりなどのコントロールをすることで、味にも変化を持たせることができます。
ですが、偏った味になりにくく、バランスの良いコーヒーが淹れられますよ。
すっきりよりも、やや重みを感じるどっしり系に偏ったコーヒーになります。
※Kalita(カリタ)は、台形型のようでもあり、円錐(えんすい)型のようにも見える、特殊な形状をしたドリッパーも販売しています。
「ウェーブ式ドリッパー」と呼ばれるこのドリッパーは、ウェーブのようなヒダが入った、専用の波型フィルターを使用します。
ドリッパー本体にはリブはありませんが、この波型フィルターのウェーブがリブの役割を果たし、ペーパーフィルターがドリッパーに密着しないようになっているんですよ!
こちらも、人気の「カリタ式」の一つとして知られています。
「ハリオ式」
「ハリオ式」は、円錐(えんすい)型のドリッパーです。
リブの形状は、上から下までしっかり入っていて、穴に向かって螺旋(らせん)状になっているタイプです。
穴の数は一つで、コーヒー液が出る出口は大きいです。
穴の数は一つ、さらに大きいので、お湯の注ぎ方を変えることで、コーヒーの抽出速度を変化させることが出来ます。
お湯のコントロールにより、様々な味わいを楽しめるため、プロのバリスタからも高い支持を得ています。
お湯を注ぐ速さ、注ぐ回数やタイミングなど、自分次第でアレンジ出来ます。
慣れは必要かもしれませんが、ある程度で大丈夫!
気軽にトライしてもらいたいです。
台形型と比較すると、お湯がカップやサーバーに落ちる速度が早いことにより、雑味の少ない味わいになる傾向があります。
バランスが良いというより、キレを感じる、すっきりとした印象のコーヒーに仕上がります。
「コーノ式」
「コーノ式」は、「ハリオ式」と同じ円錐(えんすい)型のドリッパーです。
リブの形状は、下部のみの直線で、上部には無いタイプです。
穴の数は一つで、コーヒー液が出る出口は大きいです。
(「コーノ式」の穴の大きさを、「ハリオ式」と画像で比較してみましたが、「ハリオ式」の方が大きいように見えました)
お湯を注ぐと、リブの無い上部ではペーパーフィルターがドリッパーに密着しますが、下部に設けられたリブが、お湯の抜けをスムーズにしてくれます。
「ハリオ式」と同様に、注ぎ方でコーヒー液の落ちる速度に変化を付けることが出来るドリッパーになります。
味わいの傾向は、どっしりとしたボディ感を感じます。
また、リブの無い上部で、アクや雑味が吸着されるので、後味のキレが良い、クリアな印象のコーヒーに仕上がりますよ。
いかがでしたか?
メーカーそれぞれにドリッパーの特徴があり、それに応じて味わいにも違いが見られましたね!
比較してみて、自分の好みの味が出せそうなドリッパーを選んでくださいね♪
職人気質の強い日本では、色々な器具が生まれ、ハンドドリップの文化が根付いています。
海外ではエスプレッソを使ったドリンクが主流のように見えますが、日本製のHARIO(ハリオ)やKalita(カリタ)を使ったカフェも多くあるようですよ!
これらの中で「一番良いドリッパー」はありません。
違うタイプのドリッパーが揃えば、その時に飲みたいコーヒーの味をイメージして、使うドリッパーをチョイスすることも出来ます。
コーヒーの楽しみ方や満足度が、一気に高まりますよ♪
【おすすめ4選】人気コーヒードリッパーを、定番メーカーごとにご紹介
有名なメーカーのドリッパー、「メリタ式」「カリタ式」「ハリオ式」「コーノ式」について触れてきました。
では、各メーカーから、具体的にどんな製品が販売されているのでしょうか?
次からは、それぞれのメーカーごとの、定番コーヒードリッパーとその特徴をご紹介していきますね!
ぜひこちらもご参考にしてください。
1. 【Melitta(メリタ)】「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」
Melitta(メリタ)の「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」は、穴の位置がポイントです。
通常だと、穴は底面に付けられますが、「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」の場合、底よりも少し高いところに付けられています。
この穴の位置のお陰で、「蒸らし」がしっかりと行われます。
(「蒸らし」は、コーヒー粉とお湯を触れ合わせて一定時間(30秒ほど)置いておく、ハンドドリップの工程です)
注いだお湯が一旦、底に溜まるので、抽出時間も比較的 長くなります。
この製品名通り、コーヒーのアロマを深く引き出せるのです。
また、この「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」は、お湯を何度かに分けて注ぐ必要がありません!
「蒸らし」の後は、リブと小さい一つ穴のドリッパーが、お湯の流れをコントロールしてくれます。
細かい工夫が不要なので、誰でも簡単においしいコーヒーを抽出できます。
初心者にとっては、お湯を注ぐ回数やタイミング、悩みますよね。
杯数分に合ったお湯を注ぐだけでOKという手軽さは、他のドリッパーには無い大きな魅力です。
淹れる人の技術を問わない「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」の特徴3つ、こちらにまとめました。
【Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1 の特徴3つ】
- 一つ穴、かつ穴自体も小さいことにより、お湯が底に溜まり、一定の抽出速度が保たれる
- 味に変化はつけにくいが、その分、ハンドドリップドリップの技術を問わず味わいが一定のコーヒーを淹れられる
- ハンドドリップ専用の口が細くなっている「細口ポット」が不要!手持ちのヤカンでも美味しくドリップ可能
2.【 Kalita(カリタ)】「101-D」
日本生まれのメーカー「Kalitaカリタ」の「101-D」は、販売されているドリッパーの中でも最もポピュラー!と言っても良いでしょう。
台形型のタイプのドリッパーで、リブは上から下まで直線、底の穴は三つです。
Kalita(カリタ)「101-D」は、大きなコーヒー専門店などに行かなくても、スーパーのコーヒーコーナーでも手に入ります。
道具が手軽に入手できる、ということもあり、なんとなく買ったものが実はKalita(カリタ)の「101-D」だった、という人もいると思います。
注ぐ人による味のブレが起きにくいので、安定したコーヒーが淹れられるのが特徴です。
こちらが、Kalita(カリタ)「101-D」の特徴3つです。
【Kalita(カリタ)「101-D」の特徴3つ】
- 台形型、三つ穴、上から下までついているリブにより、コーヒーの抽出速度はやや早めになる
- やや早めの抽出速度なので、バランスを保ちながらある程度はコーヒーの味に変化をつけられる
- 取り扱いをする身近な販売店が多い上、値段も500円以下で安く、手に入りやすい
3. 【HARIO(ハリオ)】「V60透過ドリッパー01クリア」
「HARIO(ハリオ)」の「V60透過ドリッパー01クリア」は、世界中のバリスタが愛用し、ハンドドリップの世界大会でも使用されているドリッパーで、大変有名です。
特殊な布で作られた布製のドリッパーで淹れるコーヒー「「ネルドリップ」のような、本格的な味わいを出すことが出来ます。
円錐(えんすい)型の「V60透過ドリッパー01クリア」にコーヒー粉をセットした場合、コーヒー粉の層に高さが出来ます。
高いコーヒー粉の層の中を、お湯がじっくりと通過するので、旨味の詰まったコーヒーオイルが多く抽出されるんですよ。
このため、ネルドリップに近い、なめらかな口当たりのコーヒーが抽出できます。
ネルドリップはネルフィルターのお手入れに少し手間がかかりますが、ペーパーフィルターを使用する「V60透過ドリッパー01クリア」なら後片付けもとっても簡単!
ペーパードリップの手軽さと、ネルドリップの美味しさを両立させたドリッパーです。
こちらが、HARIO(ハリオ)「V60透過ドリッパー01クリア」の特徴3つです。
【HARIO(ハリオ)「V60透過ドリッパー01クリア」の特徴3つ】
- 台形型のカリタ式やメリタ式に比べると底の穴が大きく、注いだお湯が溜まらずにスムーズに落ちる
- お湯を注ぐ速度を早くしたり遅くしたりすることができ、味の変化を楽しめる
- ハンドドリップへの慣れ、ある程度の技術は必要になるものの、その分 味わいをコントロール出来る
4.【 KONO(コーノ)】「MDK型 名門二人用フィルター」
KONO(コーノ)「MDK型 名門二人用フィルター」は、2015年 KONO(コーノ)の創業90周年を記念して作られたモデルです。
KONO(コーノ)独特の形状である下部のみのリブは、これまでも膨大なデータを用いて改良が続けられてきました。
今回の「MDK型 名門二人用フィルター」では、下部のリブをこれまでよりも短くし、コーヒーの風味がさらに抽出されるような設計です。
HARIO(ハリオ)「V60透過ドリッパー01クリア」と同じ円錐(えんすい)型で、ネルドリップのような味わいを手軽に楽しむことが出来ますよ!
ただ、KONO(コーノ)の場合、ドリッパーに合った特殊な淹れ方します。
それは、通常のような「蒸らし」は行わず、コーヒー粉の中心に1滴ずつお湯を垂らす「点滴ドリップ」と呼ばれる方法です。
KONO(コーノ)「MDK型 名門二人用フィルター」でコーヒーを淹れる場合は、この「点滴ドリップ」で挑戦してくださいね。
こちらが、KONO(コーノ)「MDK型 名門二人用フィルター」の特徴3つです。
【KONO(コーノ)「MDK型 名門二人用フィルター」の特徴3つ】
- リブが下部にしかないことで、コーヒー液の落ちる速度が調節され、コーヒーの味・風味が逃げずに抽出される
- ネルドリップと同じように、お湯の注ぎ方で味わいに変化をつけられる
- 「コーノ式」に合った、「点滴ドリップ」と呼ばれる方法で淹れると、美味しく淹れられる
コーヒードリッパーを選ぶ時のコツ
使い方やタイプに注目すれば、自分に合ったものが選びやすい
定番メーカーが販売するコーヒードリッパーそれぞれの特徴的な形状と、具体的な製品名を4種類ご紹介してきました。
自分が好きな味を出せそうなドリッパーが絞れてきたのではないでしょうか?
次からは、「どのような使い方をしたいか?」を考えながら、コーヒードリッパーの選び方を見ていきたいと思います♪
3つの使い方と、それに合ったタイプのおすすめのメーカーと、ドリッパー名をご紹介しますね。
それぞれにメリット、デメリットあると思いますが、どんな使い方をするのか、あらかじめイメージしながらドリッパーを選びましょう。
そうすることで、より自分に合ったドリッパーに出会えますよ♪
「淹れ方をコントロールしながら、幅広いコーヒーの味の変化・違いを楽しみたい!」
という人におすすめのドリッパー
ただハンドドリップをするのではなく、日々淹れ方を工夫して、上達する喜びを味わいたいという人もいると思います。
「せっかく挑戦するなら、探究しながら自分の腕を上げていきたい」「淹れ方をコントロールして、味の違いも一緒に楽しみたい」という人には、味に変化をつけられるドリッパーがぴったりです。
このようなドリッパーの使い方をしたい人は、「カリタ式」や「ハリオ式」「コーノ式」が良いですよ♪
中でも、ハリオ式が特におすすめです。
注ぎ具合を幅広く自分でコントロールし、さっぱりからコクのある味まで味わえます。
お湯を落とす速度を調整するのは、慣れないうちは苦戦するかもしれません。
ですが、淹れていくうちに、コーヒーの味の変化・違いを幅広く楽しめるようになりますよ!
ハンドドリップの醍醐味を存分に味わいましょう。
「機能性、こだわりを感じるおしゃれなデザイン どちらも大切!」
という人におすすめのドリッパー
ドリッパーを選ぶ際に、「機能性を大切にしたい」という人は多いと思います。
それに加えて、ユニークでおしゃれであることも、選び方の大事なポイントです!
気に入っているデザインのものは、ハンドドリップの時間をより充実させてくれるアイテムになりますよ。
こちらに、デザインが素敵なドリッパーのメーカーを4つ、ご紹介しますね。
デザイン重視のドリッパーを選ぶ際の参考にしてください。
【TORCH(トーチ)】
「TORCH(トーチ)」は、元喫茶店のオーナーである、中林 孝之さんが立ち上げたメーカーです。
大変有名なのが、「マウンテンドリッパー」、「ドーナツドリッパー」の2つのドリッパーです。
どちらも角度が鋭い円錐(えんすい)型ですが、丸みも帯びていて、優しい雰囲気があります。
限定色の販売もあるようですが、基本は白と黒。
インテリアのアイテムとしても、スッと空間に馴染む、可愛らしいデザインが魅力です。
【CHEMEX(ケメックス)】
「CHEMEX(ケメックス)」は、アメリカ生まれのドリッパーです。
ドリッパー部分と、コーヒー液を受けるサーバー部分が緩やかなカーブを描きながら繋がっているデザインです。
本体はガラス製で高級感がありますが、真ん中の繋ぎ目の部分は、温かみがある木片と革の紐で固定されています。
芸術品のように美しい一体型のデザインは、愛好家も多い逸品です。
そのデザイン性の高さは、美術界でも認められているほど。
ニューヨーク近代美術館(MoMAの愛称で有名)、ブルックリン美術館において、パーマネントコレクションに認定、収蔵されています。
(パーマネントコレクション: 選定されると、以降 永久的に収蔵されます)
【ORIGAMI(オリガミ)】
「ORIGAMI(オリガミ)」は、ドリッパー本体にリブがほどこされていて、まるで折り紙を折って作られたようなデザインです。
シャープで、ピシっと入った折り目(リブ)は、とっても美しいです。
一風変わったデザインは、国内外のプロのバリスタの声を反映させて完成したそうですよ。
【ZERO JAPAN(ゼロジャパン)】
「ZERO JAPAN(ゼロジャパン)」は、陶器製のコロンとした見た目が可愛いドリッパーです。
ドリッパーだけでなく、同じ系統のティーポットも、豊富なカラーで人気です。
シリーズで揃えて、コーディネートも楽しめそうです。
個性豊かなコーヒードリッパー、色んなメーカーから販売されていますね。
今回ご紹介したメーカーは4つだけですが、まだまだたくさんあります!
後ほど、より詳しく触れていきたいと思います。
代表的なメーカーも視野にいれつつ、その他の色々なコーヒー器具のメーカーにも注目してみてくださいね♪
「手軽に安定した味わいのコーヒーを淹れたい!」
という人におすすめのドリッパー
「テクニックが必要なプロのような淹れ方はしなくて良い」「色々こだわらず、美味しいコーヒーをさっと淹れたい」という人も、きっと多くいると思います。
こういう方は、ブレずに安定した味が出せる「メリタ式」がピッタリです!
メリタ式のドリッパーは、蒸らしの後は、お湯を一度に注ぐだけでOK。
『【おすすめ4選】人気コーヒードリッパーを、定番メーカーごとにご紹介』でも触れましたが、メリタ式であれば、コーヒーを淹れる際の細かい調整は一切不要です。
代表的な「Aroma Filter(アロマフィルター)AF-M 1×1」の他にも、メリタ式のドリッパーは色々とあります。
どのタイプのドリッパーも、お湯の注ぎ方に影響を受けにくく、抽出の速度は安定しています。
「初心者向け」と言われるドリッパーは存在する?
「手軽に安定した味わいのコーヒーを淹れたい!」という人には、「メリタ式」がおすすめであるとお伝えしました。
「ペーパードリップが全くの初心者です」という人にも、同じく「メリタ式」のドリッパーが人気です!
Melita(メリタ)のドリッパーは注ぐ人の腕に左右されずに安定したコーヒーが淹れられます。
「どれが美味しく淹れられるの?」と悩んでいる人や、「ハンドドリップって難しそうだな」というイメージを持たれている人でも安心です。
台形型で直線のリブ、小さい一つ穴で定着しているMelita(メリタ)のドリッパーですが、1908年の創業から、何度も改良を重ねて現在の形状になったそうですよ。
ドリッパー内にお湯が溜まりやすく、小さい一つ穴から安定したスピードで落ちてくれる台形は、初心者に優しい設計です。
円錐(えんすい)型で、大きめの穴が空いているHARIO(ハリオ)やKONO(コーノ)のようなドリッパーは、味に変化が出やすく、一定の味を出すには難しく感じる人もいるかもしれません。
まずは台形型のMelita(メリタ)でお湯の注ぎ方に慣れて、円錐(えんすい)型に挑戦するのも手です。
ハンドドリップを繰り返していくうちに、だんだんと上手に淹れられるようになりますよ!
いろいろあるおしゃれなドリッパーは、コーヒータイムをより楽しいものにしてくれる
おしゃれなドリッパーは、コーヒーの道具としてだけではなく、気分を上げてくれる相棒となってくれます。
見た目重視で楽しくハンドドリップをしたい人は、ぜひ、材質にも注目してみてください!
手軽に使えるドリッパーの材質で人気なのは、なんと言ってもプラスチック製。
低価格で軽く、落としても破損の心配が少ないです。
扱いやすくて人気ですが、おしゃれ度をもっと上げたい人におすすめなのが、陶器製です。
ご紹介した、「Melitta(メリタ)」「Kalita(カリタ)」「Halio(ハリオ)」の3つのメーカーには、陶器製のドリッパーが販売されています。
(KONO(コーノ)のドリッパーは、アクリル樹脂製のみで、陶器製はありません)
また、ドリッパーの材質は他にも、ステンレス製、クリアなガラス製などもあり、コーヒーを淹れる雰囲気を一気に高めてくれますよ。
それぞれの材質によりメリット、デメリットがあるので、それらを考慮しながら、自分好みのデザインをチョイスしてくださいね。
『コーヒードリッパーを選ぶ時のコツ 使い方やタイプに注目すれば、自分に合ったものが選びやすい』でも触れましたが、ここで今一度、おしゃれなドリッパーについて、より深くご紹介したいと思います!
torch(トーチ)、Chemex(ケメックス)、ORIGAMI(オリガミ)、ZERO JAPAN(ゼロジャパン)の4つです。
【torch(トーチ)】
torch(トーチ)のドリッパーは、落ち着いたナチュラルな雰囲気があります。
「マウンテンドリッパー」、「ドーナツドリッパー」と呼ばれる2つのドリッパーで有名ですが、どちらもシンプルで淡い色味です。
実は、torch(トーチ)のドリッパーは、岐阜県南部の伝統ある焼き物、※「美濃焼(みのうやき)」で作られているんです。
※(白磁とも呼ばれます)
コーヒーを淹れるための道具に留まらず、日常で使う食器のように、美しさや上品さも感じられます。
形状やリブ、穴の大きさなどの構造に工夫が施されているため、機能面でも高く評価されています。
torch(トーチ)のドリッパーを使用すると、しっかりとした濃い目だけれど、重くないコーヒーが淹れられます。
付属のドリッパーを支える受け部は、ビーチ無垢材(ウレタン仕上げ)なので、更に優しい印象を与えています。
【Chemex(ケメックス)】
Chemex(ケメックス)のドリッパーは、その美しい見た目から、TVドラマのセットの一部としても登場する程です。
上部のドリッパーと下部のサーバー部分が一体化した、フラスコ型のフォルムは、1941年に誕生したそうです。
余分なものがないので、時間をかけて考え抜かれたデザインのように見えますよね。
ですが、実はアメリカの科学者が実験室のフラスコを、コーヒーメーカーとして代用したことから誕生したそう!
80年以上経った今でも世界中で愛されているデザインが、気まぐれの発想だったとは、とっても面白いですね。
また、Chemex(ケメックス)を特別に感じさせてるのが、専用ペーパーフィルターです。
この専用ペーパーフィルターは、一般的なフィルターと比較すると、30%以上の厚みを持たせて作られています。
正方形のただの紙に見えますが、ドリッパー部分に差し込むことで、円錐(えんすい)形になるんですよ。
Chemex(ケメックス)で淹れたコーヒーの味わいは、ボディ感があり、クリーミーさや甘さを強く感じます。
【ORIGAMI(オリガミ)】
ORIGAMI(オリガミ)ドリッパーは、折り紙を折ったような個性的な見た目がおしゃれなポイントです。
さらに、そのカラーバリエーションの多さも、大きな魅力です!
陶磁器製だと10色以上、AS樹脂製では5色以上の中から、自分の好みのものを選べます。
色違いでいくつも持っている人もいます。
折り目を重ね合わせて伏せておいておくと、とっても素敵ですよ。
(限定色の販売も随時行なっているようなので、ぜひ、公式サイトでチェックしてくださいね!)
【ZERO JAPAN(ゼロジャパン)】
ZERO JAPAN(ゼロジャパン)は、岐阜県土岐市に拠点を置く、陶器メーカーです。
1992年に誕生し、当初はコーヒー豆を保存する容器などを、アメリカに向けて開発・販売を行なっていたそうです。
現在では、ティー関連にも製品の幅を広げて、世界46か国で販売されています。
世界でも通用するようなデザインとカラーは、ドリッパーにも生かされています。
ドリッパーに付いている持ち手は緩やかなカーブを描いていて、他には無い独特なデザイン。
厚みのある磁器はとっても丈夫な上、ドリッパー底部には、ドリップした量が一目で分かるように窓が空いているデザインです。
5色以上の中から、自分にぴったりなカラーを選ぶことが出来ます。
最後に...|コーヒードリッパーごとに味わいが変化する!
お気に入りをみつけて、さらにハンドドリップを楽しもう
いかがでしたか?
ドリッパーの選び方をテーマに、ドリッパーの種類・形状の違い、有名メーカーの特徴、おしゃれなドリッパーの種類まで、幅広くご紹介してきました。
大切なのは、「自分はどんな味のコーヒーが好きなのか?」です♪
その味わいを出せる特徴を持ったドリッパーを選べばOK!
また、「淹れ方をコントロールしたい」「魅力的なおしゃれなドリッパーが良い」「安定したコーヒーを淹れたい」という目的を考えると、自分に合ったドリッパーを選びやすくなりますよ!
初心者向け、機能・おしゃれなデザインが両立しているものに絞った選び方も出来ます。
ドリッパーはシンプルな構造のコーヒー器具です。
ですがこのように一つ一つ紐解いていくと、実はかなり奥深いアイテムだ、ということも理解できたのではないでしょうか?
コーヒーの味を左右するドリッパーの特徴を知り、お気に入りのドリッパーが見つかれば、家で淹れるコーヒーの時間がより楽しめるでしょうね!
ひとつのアイテムの使い勝手、味の違いに慣れたら、異なった形状のドリッパーを試すのも、面白いですよ!
色んなタイプのドリッパーを試すことで、さらに深くコーヒーの世界に浸れます。
ぜひ、今回の記事を参考に、ドリッパー選びを楽しんでくださいね!
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
ten to ten(テントゥテン)では、今後も「自分好みのコーヒーに出合う」をテーマに、コーヒーに関する情報をお届けしていきます。
その他の記事も、ぜひ参考にしてくださいね!
また、次回の記事でお会いしましょう!